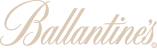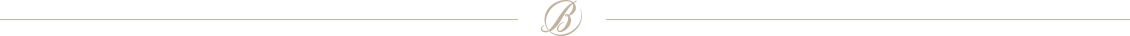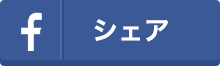アールデコを基調とした豪奢な内装の中にいる自分が不思議でしょうがない。だからといって居心地が悪い訳でもなく、期待感に満ちた自分がいて、それも不思議だった。気になっているのは身につけているジャケットだった。年に数えるしか着ることがなく、慣れていない。そのため肩が凝る。
大好きなウイスキーのオン・ザ・ロックをオーダーすると氷に仕掛けがあった。氷の中に白く輝く模様が入っている。
「これ、何かの模様ですか」
八峰が尋ねると、ラウンジ、バー支配人の本多が笑みを浮かべながらジャケットの左襟に付けたピンバッジを指差しながら言った。
「当倶楽部のロゴマークです。メンバーの方に限り、このロックアイスでサービスさせていただいています。ゲストご同伴であったとしても、メンバーの方にしかこのアイスは使いません」
まる氷ができ上がる前にロゴマークの型取りという手間がかかっている。「うーん」と感心した唸り声を八峰は発しながら、特別な扱いに嬉しいような気恥ずかしいような心持ちになった。飲み慣れたウイスキーの味わいもより高まっているような気がする。ウイスキーも自分と同じように照れているのかもしれない。
台場にある東京ベイコート倶楽部ホテル&スパリゾートのメンバーとなってのデビューだ。初回の今夜は完全会員制である倶楽部内のロビーフロアにあるメインバー、モナーク バーで過ごしてみることにした。スイートルームでの宿泊やさまざまなレストラン、ラウンジ、スパなどの施設が利用できるが、見事な夜景を眺める前に、とりあえずこれまでの八峰の生活とはかけ離れた世界に慣れてみようとバーを訪ねてみたのだった。
完全会員制倶楽部の入会をすすめたのは高校時代からの友人で弁護士をしている谷村だった。「俺がそんなところに。メンバーはセレブばかりなんだろう」と言う八峰に、「会社社長だって最初は平社員、名医だってインターンからはじまる。代々つづく真のセレブなんて世界でもひと握りだよ。皆それなりに苦労してステータスを得るようになったんだ。おまえなんかもう十分なステータスがあるじゃないか。それにそろそろ奥さん孝行してもいいんじゃないか」と谷村は言った。
八峰は絵本作家として世界中に名が知られようになったが、谷村にしてみれば一向に生活スタイルの変わらない友人に新しい風を浴びさせてやりたいという思いに駆られたのだろう。そしてすでに谷村がメンバーとなっているこの倶楽部をすすめてきた。
美大を卒業してグラフィックデザイン会社に入ったもののイラストレーターの道にすすむために2年で退職した。その間に大学時代から付き合っていた女性と結婚したが、フリーではなかなか食べていけない八峰に愛想を尽かして出て行ってしまった。
30歳になった頃に八峰の絵が好きだという出版社の女性と出会う。彼女は度々雑誌記事の挿絵を依頼してきた。それがいまの妻である。
絵本作家への道へ入ったきっかけも妻だった。一日中2DKの箱の中にいて外に出ようとしない八峰に、妻は犬の散歩という仕事を命じた。近所の知り合いの老夫婦のご主人のほうが病気になり、飼っている老いたゴールデンレトリバーの散歩ができなくなった。それを引き受けてきたのだった。
人懐こい犬種だと聞いていたがその通りで、すぐに懐いてくれた。若い頃のヤンチャさが失せていたことも助かった。
朝晩、老犬との散歩が八峰の日課となる。ある日、その散歩の様子を絵にしてコメントも添えて「病床のご主人へどうぞ」、とご夫人へ手渡した。老夫婦はとても喜び、散歩の犬の絵とちょっとした天気や近所の様子を伝えるコメントを楽しみにするようになった。
しばらくすると妻が出版社の児童文学担当編集者を家に連れてきた。犬との触れ合いを絵本にしないか、と持ちかけてきたのだった。妻が企画書までつくり上げていた。
乗り気ではなかったために「考えさせてください」とその場をやり過ごしたが、絵本を書くきっかけは1年後の犬の死だった。病床のご主人よりも早く老衰で亡くなる。いつかは途切れると覚悟していた散歩だったが、いざ直面するとこころにぽっかりと穴が空いたような気がした。
犬の名前はバランタインだった。老夫婦が愛飲していたウイスキーからいただいたものだ。こころの穴を埋めるかのように、そのバランタインが旅をする物語を描きはじめた。
設定は常に架空の街。人々のいさかいを解決したり、孤独な人間と触れ合ったり、不幸な子供を勇気づけたりするバランタインの姿を何話も描いた。
最初、日本では小さな話題となったがブームまでには至らなかった。ところが英訳され欧米で出版されると大きな話題となり、次々といろんな言語に翻訳されて世界的なベストセラーへと拡大し、いまもそれはつづいている。
老犬の死から10年が経つが、まだ昨日のような気がする。それは八峰の生活が以前とほとんど変わらないからともいえる。毎日自宅にこもって描いている。変わった点は2DKの住まいから老夫婦と老犬の住まいだった一軒家を譲り受けたことと、ウイスキーのバランタイン17年を飲むようになったことだ。
「やはりバランタインを愛飲されているんですね」
本多が納得したように話しかけてきた。
「ああ、ええ、そうなんです。芸がないかな」
「そんなことはございません。素敵です。わたくしの子供たちはもちろん家族皆、旅するバランタイン・シリーズの大ファンです。今度アニメ化されるそうですが、とても楽しみにしているんです」
「ありがとうございます。でもどうかな」
そう言って八峰は口ごもった。ちょっとマンネリ化してきている。いつシリーズを終えようか。最近そればかりを考えるようになった。
「八峰さんは、海外に行かれたことがないそうですが、ほんとうですか」
本多にそう聞かれて、この倶楽部の接客の見事さを実感する。海外旅行のことだけでなく、先生と呼ばれることを嫌うのを知っている。はじめてなのにメンバーの情報をきちんと把握している。本多のこの質問で八峰の肩の凝りがほぐされたような気がした。ジャケットの重さも気にならなくなった。
「はい、その通りです。自宅近辺しか知りません。絵の背景は、写真集や旅のガイドブック、それにインターネットの画像検索があるから助かっています。全部資料をアレンジして描いているんです。あとはテレビの旅番組もヒントをくれる」
そう説明しながら、思いのほか口が軽くなっている自分に気づく。
「一生、外国へ行かれる気持ちはないのですか」
「いまのところ。だって、この台場や東京ベイコート倶楽部でさえ、わたしにとっては外国みたいなものですよ」
八峰の本音ともいえるジョークに本多は微笑みながら頷くと、束の間、カウンターから立ち去った。戻ってくると手にしたウイスキーボトルが入った化粧箱を差し出した。
「こちらは、谷村先生から八峰さんへの贈り物です。いらっしゃったらお飲みいただくようにと命じられています。そしてシリーズをあと30年はつづけてくださいとのことです」
バランタイン30年だった。
「30年後、75歳になっている。描けるかな。無理じゃないでしょうか」
「読者として、わたくしお供します」
本多が爽やかな笑顔で言った。八峰は彼とは長いつき合いになりそうな気がした。妻に老夫婦、谷村、そして本多。誰かのチカラを得て、自分は生まれ変わっていくのだろう。変わらないのは、バランタインとの旅なのかもしれない。
(第18回「旅するバランタイン」了)








*この物語は、実在するホテル、ホテルバーおよびバーテンダー以外の登場人物はすべて架空であり、フィクションです。
登場人物
八峰(絵本作家)
 協力 リゾートトラスト株式会社
協力 リゾートトラスト株式会社
東京ベイコート倶楽部
ホテル&スパリゾート