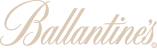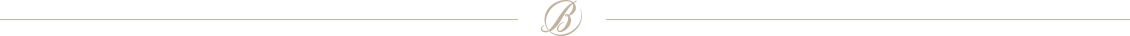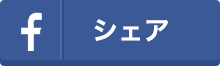カウンターに近いソファー席に案内されて杏子は安堵した。他の席からは死角といえる位置だ。女ひとり客への心遣いが嬉しい。
バーの扉に手をかけるまでは自分の行動を考えもしなかったが、土屋が「いらっしゃいませ」と丁寧に頭を下げて対応してくれた瞬間、我に返った。同時に土屋がフロアにいてくれた幸運を、心のなかで手を合わせて喜んだ。
顔には出さないけれど、土屋は杏子がひとりでやってきたことを怪訝に思っていることだろう。
ル・マーキーへはこれまで健介とふたりで訪れていた。ライトアップされたホテルの庭を散策して、そのあとには必ずこのバーで寛ぐ。
名園として知られるホテル椿山荘東京の庭は、蝋梅(ろうばい)が新春の華やぎを告げると、河津桜、啓翁桜、そして春爛漫のソメイヨシノに横浜緋桜と人を魅了しつづける。5月にはカキツバタを見て、しばらくすると最も楽しみにしている蛍が水辺を舞う。目白台という都心に近い場所とは思えない野趣がある。杏子と健介が住むマンションからは歩いて15分ほどの距離で、格好の散歩コースであり憩いの場だ。
それなのに今夜はひとりでむしゃくしゃしながら庭を歩き、咲き誇るソメイヨシノを堪能することもなく、気がついたらル・マーキーの扉を開けていた。
花冷えという寒さではなかったはずだが、ホット・カクテルが恋しい。
土屋は「おまかせください。チョコレート、お好きでしたよね」とすぐさま対応してくれた。
おまかせで登場したカクテルに杏子は思わず吹き出した。
「パフェ、じゃないですよね。ホット・チョコレートみたいですけど、上に乗っかっているのはなんですか」
「マシュマロです。シナモン・スティックで、上下にザクザク混ぜてください。チャイルズ・ハートという、わたしのオリジナル・カクテルです」
杏子は土屋に教えられたとおり、ベビー・マシュマロを沈めるようにスティックを上下させてみた。なるほど、“童心に返る”といった意味合いをネーミングに込めたのだろう。無邪気になれる、と感じはじめたところに健介の顔が浮かんできた。
疲れているんだから、疲れたといって何がいけないのだろう。「キミだけじゃない。俺だって同じだ」なんて、そんなの、わかっている。一緒に生活するようになり、5年が経つ。最近、些細なことでお互いに苛立ち、よく口喧嘩をする。どちらも引っ込みがつかなくなるのはどうしてなのだろう。
正月に実家へ顔を出したとき、母が「いい加減に籍を入れなさい。あなた今年36でしょ。健介さんは40だっけ。ときめく時間はとっくに過ぎちゃったでしょうに」と言った。父が「若い人たちには、若い人なりの考えがあるだろうから」と取りなすと、「だから、若くないって」、と母が厳しい口調で返した。父母は長年こんな会話を飽きもせずつづけている。男と女なんてそんなものなのだろう。
口に含むと、ホット・チョコの甘い香りが浮遊した。ナタデココを想い起こさせるマシュマロの食感には遊び心がある。余韻に上質な心地よい温かみがあった。胸の内にほのかな光りがポッと灯る、そんな感覚だ。
まあ健介も撮影で疲れていたのだろうし、今日はモデルとの波長が合わなかったのかもしれない。きっと、達成感がないのだろう。わたしは昨日帰国したばかりで時差ボケだ。庭を歩いて、身体がいまやっと目覚めた気がする。夏物の買い付けはうまくいったけど、パリはまだ寒くて疲れた。
「お気に召したようで。どういたしましょうか、次の一杯は。桜をイメージしたカクテルでもおつくりしましょうか」
土屋が微笑みながら声をかけてきた。
「ええ、次もおまかせします。おいしくて、いつの間にか飲んでしまいました」
「かしこまりました。そういえば、庭の幽翠池(ゆうすいち)の水面に映ったソメイヨシノ、いかがでした。奇麗でしたでしょう」
これには頷いて誤魔化すしかなかった。池に映る紅葉も桜も健介とふたりで見てきたのに、今夜は、何も見えてはいなかった。
二杯目のカクテルには桜の花が浮かんでいた。バーの淡いライトの光に包まれた紅色が幻想的だ。幽翠池に映る夜桜をイメージしたのだろうか。
「美しい。飲まないで飾っておきたいくらい。カクテル名はなんですか」
「実は即興でして、まだ名前はありません。これから考えます」
ひと口啜る。桜の風味が口中に甘く優しく広がる。胸にふたたび温かさが満ちた。
「独特の余韻があるんですね。上品な温もりが。何が使われているんですか」
杏子がそう訊ねると、土屋が頷きながら微笑んで言った。
「ベースはスコッチのブレンデッドウイスキーです。バランタイン17年。先ほどのチャイルズ・ハートにも使っています」
バランタイン17年。健介が最近、オン・ザ・ロックで飲むようになった。ウイスキー好きの健介だが、とくにこれといって贔屓の銘柄はなかった。昨年末に土屋とウイスキー談義をする中で「華やぎのなかに複雑味があり、それでいて重くなく、飲み飽きない。なによりも上質感があります」とすすめられて試し、気に入ってしまった。そのとき健介は「こういうウイスキーが似合う大人に憧れていた」と言った。
「どうなの、バランタイン17年が似合う大人になってきたかしら」
「自分ではわからない。でも飲みながら、いい大人に熟成していけるような気がする」
そんな話をしたのは、梅の花を見に来た夜だった。なんだか悔しいけれど、そうか、バランタイン17年の温もりだったのか。
つまんない口喧嘩で、衝動的に飛び出してきちゃったな。桜にも申し訳ない。しっかりと鑑賞しなくっちゃ。
「失礼いたします。お連れ様がいらっしゃいました」
土屋がそう声をかけながら手を差し伸べた向こうに健介が立っていた。杏子は驚いて、思わず立ち上がりそうになった。それでも平静を装うつもりだったが、慌ててしまい「ど、どうしたの」と、声がうわずってしまう。
健介は照れを隠そうともしないで、下手な嘘を言った。「庭を歩いていたらバランタイン17年の香りがしてさ。飲みたくなって」
「わたしは感じなかったけれど。いったい、どんな香り」
嬉しい気持ちを見抜かれないように、わざと意地悪く返した。
「甘美で、華やぎがあって、春の野のようなスパイシーさもあって、そのぉ、花見にふさわしい香りだよ。そうですよね」
突然に同意を求められ、土屋は困惑した顔を一瞬見せたが、すぐにこう返した。
「あるベテランバーテンダーの名言があります。“いい女と、いい酒は、迎えに行け”と」
土屋までもが照れたようにそう言うと、健介のオン・ザ・ロックをつくりにカウンターのほうへと向かった。
(第1回「ウイスキーの花影」了)








*この物語は、実在するホテル、ホテルバーおよびバーテンダー以外の登場人物はすべて架空であり、フィクションです。
登場人物
杏子(アパレル企業勤務)
健介(写真家)
 協力 ホテル椿山荘東京
協力 ホテル椿山荘東京