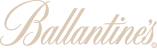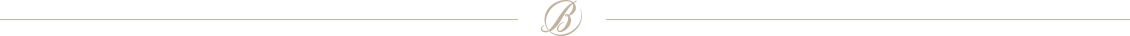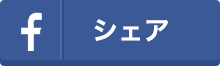カウンター席に座り腕時計を見ると19時前だった。五月の陽は長く、天窓からはまだ明るい光が注がれている。
「高層階だからこの時間になっても陽が射し込んで、明るいのだろうね」
島村は馴染みのバーテンダー、丸田に話しかけた。
「吹き抜けの天井高が27メートルありますから開放感も手伝っているのだと思います。これから夏にかけて、夜の気配にはもうしばらく時間がかかります」
そうか、そうだった。街場の行きつけの小ぢんまりとしたバーも頭に浮かんだのだが、今夜はこの開放感の中でこころを癒したかったのだ。
せせらぎを配した広い空間の中で、島村が腰を落ち着けたカウンター席はやすらぎの岸辺といえた。
「来月はもう夏至か。ああ、夏がやって来るんだな」
「はい。いまがいちばん爽やかな季節ですし、それに今夜は満月です。月あかりに照らされた、いい夜になりそうです」
ストリングスホテル東京インターコンチネンタルはJR品川駅に直結する品川イーストワンタワーの26階から32階に位置している。26階のロビーフロアにあるTHE DINING ROOMのバーカウンターは、坂崎との待ち合わせ場所でもあった。
坂崎は島村と同業の古美術商で、彼は京都で店を営んでいた。東京にやってくると必ずここに宿泊する。新幹線の便だけでなく、このホテルのチャイニーズ・レストラン「CHINA SHADOW」の良質な素材と優しい味付けを好んでいた。さらにあるとき、坂崎と同じように丸田が学生時代に空手をやっていたことを知り、息子のような年頃のバーテンダーを特別贔屓にしはじめる。そして島村を呼び寄せては無駄話に興じた。
ジン・トニックを島村の前に置きながら丸田が何気なく言った。
「今夜は坂崎さんとご一緒ではないのですか」
島村は言葉に詰まったが、ひと呼吸おき、あえて感情を抑えて淡々と答えた。
「亡くなったよ。昨日、告別式だった。京都からいま帰ってきたところなんだ。疲れていたのだが、何故かここにきてしまった」
丸田は呆然として、言葉を失っている。なんとか、「信じられません。ご冗談が過ぎますよ」と彼らしい生真面目な物言いで返してきた。
「心筋梗塞だ。剛健な肉体を誇っていたはずなのに。それにわたしより三つも若い。67歳。若過ぎる」
長い沈黙がふたりを包んだ。姿勢を正して真っすぐに遠くを見つめていた丸田は、しばらくして声の震えを抑えるように絞り出しながら「素敵なお客様でしたのに」と発した。
島村は開放感に浸ろうと考えた自分を責めた。告別式後の京都での時間と帰りの新幹線の中で、一生懸命こころの整理をしたではないか。いくら坂崎が贔屓にしていたからといって、丸田まで悲嘆に誘うことはない。
先月も坂崎とここで飲んだ。そのとき島村に諭すようにこう言っていたのを思い出す。
「別れた奥さんとよりを戻す気など、とっくにないのはわかります。とはいえ、息子さんとはお会いになられたらどうですか。島村さん、ひとりのままで生涯を終えるんですか。せめて息子さんと連絡を取り合えるくらいの仲になられたらどうです」
島村はひとり息子がわずか3歳の時に離婚した。以来、一度も息子に会ってはいない。会えば、親の身勝手に、余計に翻弄されつづけることになると思い、きっぱりと身を引いた。
離婚後、それでも息子の進学や、成人、結婚と節目の時には短い手紙と写真が送られてきた。だから成長ぶりはなんとなくわかっている。誰が見ても母親似で、いくつになってもそれは変わらない。最後は10年ほど前、孫の誕生の知らせだった。息子夫婦、赤児が収まった幸せそうな写真だった。
「いまさら、父親ヅラできるかい。わたしに会いたい訳がない。馬鹿なこと言うな」
「格好つけなくて、よろしいと違いますか」
こんなお節介を言う奴はもういない。あの会話の夜が彼との最後の酒になった。やるせなさを払うようにジン・トニックを喉に流し込んだ。しなやかな切れ味。坂崎が好きだった風味だ。
仕事中であるために感情を強く表に出せないで耐えている丸田の顔を直視することができず、「いつものウイスキーをいただこうか」と言いながら島村は斜めうしろのテーブル席のほうへ顔を向けた。瞬間、息を飲んだ。
白人男性ふたりと談笑しながらウイスキーのグラスを傾けている日本人に見覚えがあった。誰かに心臓を鷲掴みにされたような気がした。
男は仕立てのいいスーツを着ている。靴は上等なイタリア製だろう。胸を締め付けられるような気持ちが幾分やわらぎ、安堵感が滲んでくる。しっかりとした仕事をしているようだ。
「球形の氷が収まったグラスからは気品が香り立っていた。島村は大好きなウイスキーをゆっくりと舌で転がし、華やぎのある口中香を愉しんでこころ落ち着かせてから丸田に聞 いてみた。
「あそこの席の彼、あの日本人は常連客かね」
「ええ、時折お見えになります。お知り合いの方ですか」
「いやいや、そうじゃないが。ウイスキーを飲む姿がなかなか素敵だな、と」
島村は慌てて嘘をついた。
「海外からのお客様をお連れになられることが多いのですが、ワインにしろ、ウイスキーにしろ、上質なお酒をよくご存知で、いつも皆さまを満足させていらっしゃいます」
「ほう、たいしたものだ。まだ40ちょっとだろう。商社マンかな」
「かつては。いまは独立されて、会社を経営なさっているようです」
なんの会社をやっているのか、と訊ねようとしたが、バーテンダーはこれ以上のことは決して答えまい。また変に詮索すれば、嫌な客となる。
「そういえばあちらのお客様は、お母様から、上等な靴を履きなさい、上等なお酒を飲みなさい、と言われつづけてきた、とおっしゃっていました」
丸田のその話に、島村の胸には熱いものがこみ上げ、炎のように揺らめきはじめた。
それは島村家の家訓のようなものだった。商売を立ち上げた祖父が、島村の父親にはもちろん、孫の島村にも飽きるほど繰り返した言葉だった。結婚当初、幾度か妻に「上等な靴を履け、上等な酒を飲め、と口うるさかった」と島村はこぼしたことがある。
あいつは、わたしと同じウイスキーを飲んでいる。
「ウイスキーはいろいろ試されたそうですが、ここ数年でもう決ってしまったと。どこか島村さんに通じるものがありますね。バランタイン17年を好まれる方に香る粋というの でしょうか。しっかりとした自分をお持ちです」
そう語る丸田に、彼は、あいつは、わたしの、と応えそうになり、島村は奥歯を噛み締めて耐えた。
思わず顔を振り仰ぐと、天窓に月夜の帳(とばり)がかかっていた。そこに坂崎の横顔がシルエットのように浮かんだ気がした。手元のロックグラスの氷は憎らしいほど丸く穏やかで、バランタイン17年の色を映しながら満月のように輝いている。
坂崎よ、おまえの魂は月の光になったのか。こころの中でさめざめと呟いた。
(第2回「五月の月光」了)








*この物語は、実在するホテル、ホテルバーおよびバーテンダー以外の登場人物はすべて架空であり、フィクションです。
登場人物
島村(古美術商)
 協力 ストリングスホテル東京インターコンチネンタル
協力 ストリングスホテル東京インターコンチネンタル