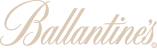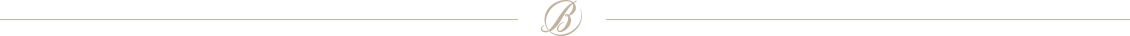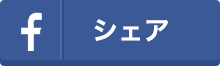12月、またひとりでカウンター席に着く。やむを得ない忘年会やパーティーへの出席がないかぎり、暮れに誰かと飲み歩くことはない。バーテンダーの坂本がその理由に触れることもない。
いつもは金彩が輝きを放つ南蛮屏風の前のテーブル席で取引関係者と談笑するか、ちょっと様子のいい女性を伴って洋の間のテーブル席のほうで男前を気取ったりしている。
「ザ・キャッスル」の常連客となって5年以上が経つが、伴った女性の数は10人を下らないだろう。女性との付き合いは長くて半年くらいしかもたない。40も半ばになり結婚する気持ちが薄らいできているのも確かだが、若い頃からどうしたものか、付き合っているうちに面倒くさくなる。いろんな人に、なんでだとよく聞かれるのだが、とにかくすべてが面倒なのだ。電話やメールのやり取り、プレゼントをされたりしたりするのがすぐに煩わしくなってしまう。自分のペースを乱されたり、自分のこころの中に踏み入ってこられたりすると、たちまちにバリアーを張ってしまう。早い話、手前勝手な人間でしかない。
かつて一度だけ坂本が、モテて、羨ましい、というようなことを口にしたことがある。「そう見えるだろうけれど、辛いんだよ。どうしたら、女性とすんなりと付き合えるんかな」と冗談めかして本音を吐露したら、彼は「世の中には氏高さんのような方もいらっしゃるんですね」とだけ返してきた。
他の連中を前にして辛いなんて口にしようものなら、会社の経営も順調で、結婚したがる女性がたくさんいて、どうして辛いのか、嫌味な奴、と責められる。ところが坂本は追い打ちをかけてこない。ホテルニューオータニ大阪が幼い頃の記憶をたくさん残す大阪城に近いこともあるが、彼のそんなところが気に入って週に2、3度は「ザ・キャッスル」で飲むようになった。
お気に入りのウイスキーをハーフロックで飲む。ウイスキーと水の1対1に氷。人がなんと言おうが、この飲み方がいちばん甘くまろやかだと思っている。無理なくおいしく何杯も飲めるのだ。
このウイスキーと、この飲み方、そしてこのバーだけは飽きがこない。それに相手が誰であれ、坂本のつくるハーフロックを飲んでさえいれば、自分を冷静に見つめつづけることができる。仕事仲間の酔いの言動に苛立つこともない。
ただやはりこの時期はこころがざらつく。いまも入り口に近いカウンター席にいる、ふたりのビジネスマンの会話が耳に入ってきた。
「息子がクリスマスプレゼントにスマホを買い替えて欲しい、って言うねん。この間買ったばかりのような気がするんやけどな」
「スマホならまだいいやんか。家なんかクリスマスに、家内と娘で海外旅行に行くんや。僕のボーナスを当てにしとんのやで」
こうした11月の会話が苦手だ。またすぐに苦い記憶がよみがえる。
小学校1年生の時にクリスマスも正月もないものになった。11月の終わりに父が出張先での不慮の事故で亡くなり、母とひとりっ子の自分のふたりだけが世間から見捨てられたような気持ちになった。
あの年の11月、ひとりぼっちの夕方に大阪城のまわりを自転車で走った。耳がちぎれそうになるほどの寒さに耐え、あふれ出る涙を風で吹き飛ばしながらがむしゃらにペダルを踏んだ。悲しいのか、淋しいのか、悔しいのか、よくわからない。わからないけれど、でっかく聳える大阪城に向かって、負けるものか、と誓っていたような気がする。
小学校を卒業するまでの間、日の暮れが早い季節、遊んでいた友だちと別れると自転車に乗ってライトアップされた大阪城を目指した。早朝から働きに出かける母が帰宅する時間まで走りまわるのが日課のようになる。
たまに夜気に包まれた自宅近くで仕事帰りの母に出くわすことがあった。毎度のように母は「あんた自転車に乗るの、好きなんやね。ほっぺた、冷とうなっとるやろ」と言いながら手袋をした手で両頬をつつんでくれた。温かくて恋しくて涙が出そうになるのを我慢して、「やめてくれ」と乱暴に言ってペダルを踏み、先に家に向かった。
母は大学まで行かせてくれた。卒業して就職した年の暮れ、はじめて母にクリスマスプレゼントをする。
高級な革の手袋を渡すと、「ありがとうな。お母ちゃん、クリスマスが大嫌いなんや。お父ちゃんが亡くなったとき、すぐに11月になって、街中に幸せそうなジングルベルが響きわたった。みじめで、腹立って。でも、これまであんたの口からクリスマスって言葉を一度も聞いたことがない。それが切のうて」と言って涙を流し、何度もありがとうと言いつづけた。
驚いたことにその夜、母もクリスマスプレゼントを用意していた。ウイスキーだった。酒屋で上等なウイスキーをください、と言ったら4本も5本もボトルを見せられたという。1本1本説明されても母はよくはわからなかったのだが、選んだバランタイン17年はラベルが気に入ったらしい。
「このウイスキー、男前やんか。名前もいかしてるし」
「でも、高かったとちがうか」
「ええねん、あんたのお金で買うたんやから。ボーナスをそっくりお母ちゃんに渡すあんたが悪いんや。でもな、こういう上等なウイスキーをいつでも飲める男になりなさい」
いまでも、人間は慎ましやかに生きるものだ、が口癖の母があのクリスマスの夜だけは 違っていた。
ふたりのビジネスマンは帰っていった。
「カウンターでひとり酒の氏高さんの姿も、なかなか味がありますね」
おそらく難しい顔をして昔のことを思い出していたのだろう。坂本が気持ちをほぐそうとしてくれているのがわかる。
「正直、12月も、クリスマスも好きやない。淋しかった子供の頃を思い出す」
突然、そう口にした自分に驚いてしまった。坂本も困惑した表情をしている。
「ごめんな。唐突に。ゆるしてくれ」
「ゆるすも、ゆるさないも。どんな思い出かはわかりませんが、氏高さんがわたしに気持ちを打ち明けてくださった。ただそれだけでとても嬉しいです」
人の良さそうな笑顔でそう言った坂本の素直な言葉を聞いて目頭が熱くなるとともに、なんだか胸のつかえが取れたような気がした。
「あれ、つくってよ。ラスティ・ネール」
「えっ。以前おつくりしたとき、錆びた釘って名前が嫌だっておっしゃったじゃないですか。わたしが俗語で、古めかしい、といった意味合いがあるって言ったら、なおさら嫌だ って」
「そうだったかもしれないが、今夜は違う。なんだか飲みたくなった」
「かしこまりました。氏高さんのために、スペシャル・バージョンでおつくりしましょう」
そう言うと坂本はミキシンググラスと小ぶりのワイングラスを用意した。
「あれ、オン・ザ・ロックのグラスに注げばいいんじゃないの」
「ですからスペシャルです」
氷が収まったミキシンググラスにバランタイン17年とリキュールのドランブイを入れ、優しく丁寧にステアする。グラスに注ぎ、レモンピールを軽く擦り、ピールをカクテルに沈めた。
口に含むと、キリッと冷えた中に懐かしいような独特の甘さが花開くように広がった。
余韻も心地よく、バランタイン17年の香味がしなやかに感じられる。
「すっきりとおいしいよ。いいね、ロックじゃないスペシャル・バージョン」
「ありがとうございます。これからはラスティ・ネールもお飲みください」
「うん。ただの古めかしい、じゃない。温故知新やな、これは。じゃあ、メリー・クリスマス」
「どうされたんですか氏高さん。それにクリスマスにはまだ間がありますよ」
「いいじゃないか、もう12月だし。今夜はこれを飲んだら帰る」
「いつもより、また随分とお早いですね」
大阪城を眺めたくなった、と応えようとしたが、ただ「うん」とだけ返した。
(第9回「メリー・クリスマス」了)








*この物語は、実在するホテル、ホテルバーおよびバーテンダー以外の登場人物はすべて架空であり、フィクションです。
登場人物
氏高(会社経営)
 協力 ホテルニューオータニ大阪
協力 ホテルニューオータニ大阪