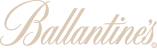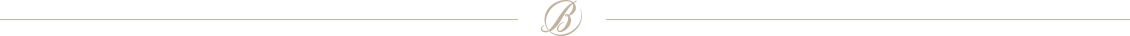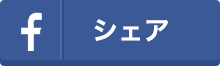人と車、そして音の波。落ち着かない。
ホテルを出て、新宿駅周辺を西口から南口、そして東口へと時計の針と逆まわりに歩いてみたのだが、行き交う人と肩がぶつかるほどに心身が過敏に反応し、硬直していく。馴染みのある街が自分を受け入れてくれないのだ。
小春日和というのに足取りは重い。ところが京王プラザホテルが近くなると急に足早になった。やっと我が家にたどり着ける、そんな安堵感が勢いを生んだのだろう。
ホテルの部屋に戻り、ベッドに倒れ込む。夕暮れ前、高層階に差し込む柔らかなオレンジ色の光の中でうとうととする。わずかな時間だったはずなのに目を開けると部屋は夕闇に包まれていた。秋の日はつるべ落とし、と昔の人は見事なたとえをしたものだ。
窓際に立ち、星屑を散りばめたような街の灯りを見つめる。たしかに時間というものは容赦がない。つるべ落としの闇がいつ訪れてもおかしくはない。
メインバーのブリアンに行くとカウンターの中にいた石部が、一瞬おっ、と身体を軽くのけぞらせ、たちまち人懐こい笑顔となって「いらっしゃいませ。お久しぶりでございます」と声をかけながら頭を下げた。
「変わらないな。きみは若いままだ」
「ありがとうございます。國村さんもお変わりなさそうで何よりです」
そう応えると、石部はかつてと同じように何も伝えなくてもウイスキーの水割りの支度をはじめた。それが嬉しかった。
ふたりだけの秘密だが、同じボクシングジムで汗を流した仲だ。國村は医学生のときに、身体がなまっていくのが嫌で、以前から興味があったボクシングをはじめた。同時期に入門してきたのが中学生の石部少年だった。彼とはすぐに親しくなり、練習後、たまにふたりで食事をした。大学生の身分で奢るといってもラーメン屋さんに行く程度だったが、中学生と話をするのが新鮮だった。
インターンになるとボクシングの時間がなかなか取れなくなる。それでも高校生になった石部の試合はできるだけ応援に行った。高校3年時の国体東京都予選での活躍には感動した。惜しくも準優勝。自分の弟が敗れたような悔しさがあり、会場から出てきた彼を涙しながら慰めはじめたら、やけにケロリとした態度が癪に触り、ゲンコツを見舞った。ただあの日だけは焼き肉を奢ったことを覚えている。
医師になり、大学病院のウイスキー好きの内科部長に連れられてブリアンでよく飲んでいたのだが、ある夜突然、かしこまった石部がいた。ホテルマンを目指すといっていたが、まさかここで出会うとは思いもよらなかった。
ボクシングのことはふたりだけの胸の内に収めた。彼には「医者だからといって、先生と呼ばないでくれ。これまで通り國村さんでいいから」と伝えた。
石部がしなやかな手さばきながら気持ちを入れたステアをし、「どうぞ」とすすめながらつづけて言った。
「やはり國村さんだとチカラが入ります。お客様の中で、いちばん緊張します。それよりも、お変わりなくこうしてお越しいただき、ほんとうに嬉しいです」
「ありがとう。でも、変わったよ。わずか1年半で、新宿をもう歩けなくてしまった。尻込みしそうな自分が嫌になってしまう」
「あちらは、やはりのどかですか」
「うん。人も車も少ない。どーん、と田園地帯が広がっている」
水割りをひと口啜る。すっきりとした味わいの中に、モルティでバニラ様が潜んだ独特の甘美な感覚が口中に浸潤する。
「いいね、石部くんの水割りは。安心感のある心地よい味わいだ」
「そうお褒めくださるのも、やはり國村さんです。以前は皆さんをお連れになって、よく飲まれましたね」
「みんな、どうしている。来てくれているかい」
「ええ、佐藤先生は國村さんを真似てボトルキープをされています」
「佐藤くんが。彼、いいとこあるじゃない」
「國村先生がいらっしゃらなくなってボトルキープのスペースがひとつ空いただろうから、とおっしゃいまして。佐藤先生もお仲間やインターンの方たちと水割りを飲まれています。ご安心ください。伝統は受け継がれています」
1年半前、郷里岩手の田舎町の総合病院に移った。日本の地方はどこも医者不足で、随分前から声がかかっていた。悩んだ末に背中を押したのは、妻と小学生のふたりの子供たちだった。
東京しか知らない妻は嫌がるだろう、と思っていたのだが、耳を疑うような答が返ってくる。「いいわ。行きましょうよ。あなたと結婚するときに、両親からこう言われたの。彼はいつか郷里に帰るというかもしれない。その日が来たときに、ハイと答える決意はあるのかって」と告白してくれ、國村の目を見つめて頷いたのだ。子供たちは「おじいちゃん、おばあちゃんの近くならいい。田んぼがあって、大きな川があって、あんなところで暮らしたい」と喜んだ。田舎育ちの自分のDNAがそう言わせたのだろうか。
周囲のほうが反対した。大学病院側の驚きようは大変なもので、かなりの引き止め工作があった。ライバル心むき出しだった佐藤が「あなたを目標にして、あなたを超えようと頑張っているのを知っていて、なぜだ」と噛み付いてきたのは意外だった。
ところが引っ越しの準備をはじめたところに東日本大震災に見舞われた。総合病院は岩手の北の内陸で、大きな被害を受けてはいなかったのだが、あの状況下で家族を連れて東北に移る決断はできなかった。一方で國村のこころには、いまこそ自分は東北に帰らなければならない、といった使命感のようなものが沸き起こる。結局は単身、郷里に帰ることになった。
「今夜は世田谷のご自宅から、わざわざお越しくださったのですか」
「いや、すでに自宅で2泊した。今夜はこちらのホテルに泊まり、明日岩手に帰るんだ。 きみの酒を飲みたくて、休みを1日多く取った」
月に最低一度は東京の自宅に戻ってきているのだが、今回の帰京には訳がある。妻からパソコンでのメールではなく封書が届いた。離婚をにおわすような内容の手紙で、上等な便せんに青いインクの万年筆で書かれた文字は皮肉なほど丁寧で美しく、余計に慌てた。
戻って話しを聞いてみると、彼女の生真面目さの中につるべ落としの闇が訪れてしまったようだ。田舎で一緒に暮らすという気持ちが薄らぎはじめ、夫を裏切ることになると思いつめ、どうしようもなくなったと言う。秋の深まりとともにこころに光が灯らなくなってしまったのだ。すべては國村自身に責任がある。自分の仕事の様子が落ち着きしだい呼ぶ、と言いながらタイミングを計りかねていた。彼女を孤独にさせてしまった自分の身勝手さを恥じるしかない。
「そうだ、伝えたいことがある。俺、ボクシングにまた首を突っ込んじゃった」
「ほんとうですか。素晴らしいじゃないですか」
「いやいや、この歳で自分がやるわけじゃない。地元の高校にボクシング部ができたんだけれど、そこのチームドクターというか、情熱ばかりが先走ってしまっている若い先生の、まあ愚痴の聞き役ってところだな」
「へぇー、青春ドラマに出てくるような役どころで楽しそうですね。これからはもっといらしてください。ボクシング部のお話を聞かせてください」
「わかった。街の喧噪に戸惑いながらも、来月もまた来る。約束する」
「きっとですよ。國村さんが愛してくださるブリアンの時間は変わることがありませんから。バランタイン17年の味わいも変わることはありません」
そう言ってつくってくれた二杯目のグラスの輝きが灯火のように思えて「この水割り、なんだか輝いて見えるな」、と國村は独り言を呟いた。石部にはそれが聞こえたらしく、「だってここは、ブリアンですから」と応えが返ってきた。
そうか、そうだ、来月はクリスマス後の帰京となる。次に来るときはつるべ落としに遭ってしまった妻を連れてこなくては。國村は心の中でそう頷いた。
(第8回「秋深き灯火」了)









*この物語は、実在するホテル、ホテルバーおよびバーテンダー以外の登場人物はすべて架空であり、フィクションです。
登場人物
國村(医師)
 協力 株式会社京王プラザホテル
協力 株式会社京王プラザホテル