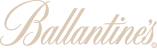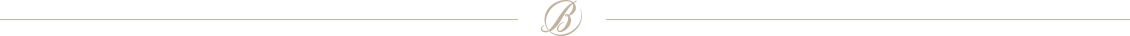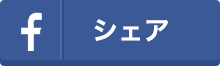懐かしい声の響きだった。6年ぶりに聞く声だった。あんなに快活だっただろうか。もっとくぐもったような話し声だったような気がする。買い替えたばかりの新しいスマートフォンのせいなのかもしれない。いや、それはいまの彼がくぐもった感じだからであって、久しぶりに耳にした昔の男の口調が新鮮に聞こえただけのことだろう。
国広が帰国した。わたしの電話番号をよく残しておいたものだ。まあ、無頓着な人だったからそのままにしておいただけなのだろう。久しぶりの挨拶らしいものもなく、「いつの間にかお互い40を超えちゃったね」のひと言は余計だし、いまさらの連絡は迷惑でしかないのだが、なんだか嬉しいような気もする。
自称アーティスト。でもいったい何が国広の得意技なのかわからない。どうでもいい風景写真を撮っていたり、へんてこりんな構図に原色のけばけばしい油絵を描いていたり、そうかと思えば雑誌にアートに関するコラムを寄稿したりしていた。付き合いだしてすぐに「お金がないから」といって甘えてわたしのところに転がりこんできた。
どう見ても稼いでいるとは思えなかったが、翻訳や通訳の仕事をしているわたしからお金を借りようとしたことはない。立派ながら不思議でもあった。2年ほど一緒に暮らしていてウザッたい存在になってきはじめる。すると、気持ちを察した訳でもなかろうに国広のほうから、ヨーロッパを旅する、といって出て行った。以来一度も連絡はなかった。少しは人間力を高められたのだろうか。
バーテンダーの安井がバランタイン17年の水割りをつくってくれると、声をかけてきた。
「英梨香さん、何か楽しいことでもありましたか。今夜はいつもと違います。女性ひとりのカウンター姿が決まっています。写真におさめておきたいくらい」
「ありがとう。でも、いつもは仏頂面して、絵にならないってわけ」
「そうは言いませんが、笑っていても、男性を寄せ付けない雰囲気はあります」
「わたしって、そんなオーラを発しているの」
「オーラってほど大袈裟じゃありませんが、森村さんとご一緒のときも、ベタベタされていませんもの」
お台場にあるホテル日航東京のキャプテンズバーの常連になったのはいまの彼、森村修嗣が贔屓にしていたからだ。3年前に修嗣との最初のデートでの食事がこのバーの奥にある中国料理の唐宮で、その後にキャプテンズバーに入り食後の酒を味わった。
あの時、カウンターを挟んで立つ安井は伸び盛りのバーテンダーといった輝きを放っていた。ウイスキー好きなので、ウイスキーをベースに甘さがありながらあと口のキレのいいカクテルをお願いしますと言うと、彼は「では森村さんのお好きなバランタイン17年をベースにしたカクテルをおつくりしましょう」と応えてスコッチキルトをつくってくれた。
バランタイン17年と、ウイスキーにハーブやハチミツを加えたスコットランドのリキュール、ドランブイにオレンジビターズをミックスしたものだった。飲んだことのあるラスティ・ネイルというカクテルに似ていて、いまの気分には甘過ぎると思えたのだが、意外にもすっきりとして切れ味がよかった。ほどよいビターズの効きとミキシンググラスでステアすることで随分と違うらしい。
安井のその味わいが気に入って、それからはキャプテンズバーにちょくちょく顔を出すようになる。オン・ザ・ロックを早いピッチで何杯も飲むわたしに水割りをゆっくりと飲むようにすすめてくれたのも安井だ。
いまでは修嗣とふたりのときよりもひとりで来ることのほうが多くなった。というのも去年、台場に引っ越してきてしまったからだ。
街場のバーもいいけれど、このホテルバーの小ぢんまりとした落ち着きを愛するようになり、安井と会話しているとお行儀よく賢い弟を相手にしているような気がして非日常の感覚がより濃くなる。引っ越したいちばんの理由はキャプテンズバーにある。
安井は歴史好きで偉人ゆかりの地を訪ねたり、美味しい飲食店を探して食べ歩いたりしていて話が面白い。仕事以外に出歩くことが少なく、気に入るとその店にしか行かなくなるわたしとまったく違う。だから飽きないのかもしれない。
「森村さん、お忙しいんですか。最近ご無沙汰ですよね」
安井が何気なく聞いてきた。わたしはウンと頷き、「春に新製品を出すんだってよ」と応える。修嗣は食品メーカーの商品開発担当で典型的な企業人だ。優男の国広とはまったくタイプが違う。マッチョで学生時代はラグビーのフォワードのスクラム一列目として活躍していたらしく、耳は餃子の形をしている。いまの趣味はトレッキング。長期休暇はヒマラヤにまで出かけていくほどだ。そしてわたしと一緒に暮らそうとも言わない。こっちとしては気が楽だ。
「あのさ、明日、昔の彼を連れてくるから、うまく対応してくれる」
安井は少し驚いた顔を見せたが、「かしこまりました」とだけ返事をした。
「よりを戻そうとか、込み入った話じゃないから安心して。わたしは結婚とかする気もないし、彼氏はひとりいれば十分。元彼のその人、海外に行っていたからね。6年ぶりに会うんだ」
「英梨香さん。まったく結婚する気はないんですか」
「そう。ない。だってひとりの男と何十年も暮らすなんてできないもの。幼稚園、小中高に大学と何人の人を好きになり、何人と付き合ってきたと思うの。社会に出てもそれはかわらなかった。その繰り返しを考えたら、ひとりの男とずっと一緒に生きるなんて不自然なことじゃない」
安井が大きくのけぞって、「そんな考え方もあるんですね」と言った。
「いいじゃない。人それぞれ。でもね、いろんな人間と付き合ったからって、ウイスキーのように麗しい熟成をするわけじゃない、ってことは確か」
「それは難しいですよね。人間にはいろんな欲があるし、他人や社会にかきまわされて、酸味や苦味の強過ぎるカクテルになっちゃうような気がします。オークの樽の中でじっとして呼吸しつづけるなんてこと、人間には無理です」
「その話、面白いよ、安井さん。そうか、そうか。人間社会がバカでかいミキシンググラスなんだね。オークの樽ってわけにはいかないのか」
「あっ、あるいは人間社会がブレンデッドなのでは。プレミアムなブレンデッドウイスキーを目指して、みんなが生きている。人がモルトウイスキーで、政治がグレーンウイスキー」
「あはは。でもチーフブレンダーはいるのかしら。神ってことになるのかな」
「そうですよね。ごめんなさい。たとえがよくないです」
安井はそういうと、新しい水割りをつくりはじめた。
「そんなことはないよ。あなたのたとえで、いろんなことを考えさせられちゃった。ありがとう」
結局わたしは独りがいいのだ。他者とブレンドし合うことなんか欲していない。たまに淋しさを覆い隠すことができればいいのだ。それが国広だったり、修嗣であったりするだけなのだ。バーでの時間もそのひとつなのだろう。
「人間は未熟成だから、麗しいものに憧れるんじゃないのでしょうか。バランタイン17年のようにしなやかな熟成感のあるウイスキーを飲んで、束の間の穏やかな時間を過ごすのかもしれません」
安井が微笑みながらそう言った。たしかに、そうなのかもしれない。わたしの人生なんて未熟成のまま過ぎていくのだろう。
(第15回「未熟な人生」了)







*この物語は、実在するホテル、ホテルバーおよびバーテンダー以外の登場人物はすべて架空であり、フィクションです。
登場人物
英梨香(翻訳家)
 協力 ホテル日航東京
協力 ホテル日航東京