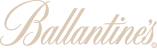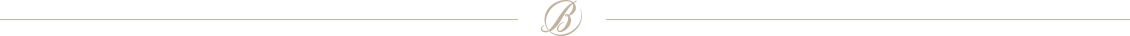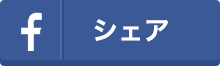うしろ姿に一瞬戸惑った。いるはずもない人に、あまりにも似ていた。長い黒髪。華奢な肩から背のライン。かつていつも身近にいた女性もそうだった。
心臓がキュっと縮まった気がした。胃から甘酸っぱさがこみあげてきたので、ウイスキーのオン・ザ・ロックで流し落とす。それでも甘酸っぱさは抗うようにこみあがってくる。またウイスキーを口にすると、むせて咳き込んでしまった。
「大丈夫ですか」
胡寺ひとりとなったソファー席のテーブル上のグラスや灰皿を片付けながら、バーテンダーの大野が心配して声をかけてきた。
「ちょっと昔のことを思い出しそうになって、感情を抑え込もうとたてつづけに飲んだらむせちゃったよ」
「甘酸っぱく、ほろ苦い思い出ですか」
大野が柔らかい口調、穏やかな笑顔で応じた。
「なんだよ。嫌な奴だな。その通り。あそこの窓辺の若いカップル。女性のうしろ姿が若い頃に付き合っていた彼女に似ているんだ」
胡寺がそう言うと、大野は窓辺のほうを見ることもなくうつむいて片付けながら頷いて、「カウンター席に移られますか」と聞いてきた。
「うん。打ち合わせも終わったし、こんな大きなソファー席にひとりでいたら、センチメンタルな気分に陥っちゃう」
「かしこまりました」
大野はまた穏やかな笑顔を見せた。
正月から2週間の予定で泊まり込んでいる。今日で10日目だ。
ザ・リッツ・カールトン東京が常宿となって3年が経つ。最初に訪ねたときはドラマの脚本書きに飽いて、気分転換とネタでも拾えればめっけものとここのバーで飲んでみた。
天井が高く、開放感がある。それに東京ミッドタウンからの見晴らしが気に入った。広い海にいるような心地を覚えた。45階でウイスキーを嘗めながら眺める景色は飽くことがない。
暮れた夜の光にあふれた時間よりも、薄暮の空、陽が沈んで間もなくの時間の眺めが胡寺の好みに合った。淡い輝きは非日常の色彩、非日常の時間、勝手にそう思い込んでいる。だから打ち合わせは夕方にし、このバーにスタッフを集める。そして陽が沈みはじめると打ち合わせを切り上げ、ひとりになる。
ラジオの構成作家に止まらず、テレビからも声がかかるようになり、いつの間にかドラマの脚本で名が売れた。いくつかの賞も得、視聴率を稼げる本書きといわれている。いまでは舞台演出まで手がけるようになった。
そんな流れを自分で欲していた訳ではない。ただひたすら書きつづけていたらいまの自分がいた。そして50歳を前になんのビジョンもない。これから自分に何が待ち構えているのか、期待もしていない。
家族がいる訳でもなく、お金の遣い方もしらない。3LDKのマンションにひとりで暮らしながら、仕事に行き詰まるとホテルに泊まり込む。周囲は優雅だとか、独り身の贅沢だとかいろいろ言っているようだが、そうなのだろうか。自分ではわからない。
ただ一日が長い。毎日毎日が長い。それだけはわかっている。
ソファー席から立ち上がり、窓辺の席の女性のうしろ姿に目を遣った。夕香の姿が重なりそうになり、すぐさまカウンターへと目を転じた。大野がオン・ザ・ロックをつくっている。足早に彼のもとへ向かった。
カウンター席に落ち着くと、すぐに大野が「どうぞ」とグラスをすすめた。
「あなたは機転が利くし、仕事が早い」
「ありがとうございます。胡寺さんの書かれる話には必ずストイックな人物が登場しますよね。主人公でなくても、わたしはその人物に感情移入してしまうんです。憧れてしまう。だからバーテンダーとして、お客様にどうリラックスしてお酒を味わっていただけるか、ストイックなまでに極めてみたいと」
「ありゃ、随分と気合いが入っているね」
「嘘です。冗談です。わたしはストイックにはなりきれません」
「そうかな。あなたなら追求できるんじゃないか」
「いや、胡寺さんのようには」
「どういうこと。俺はストイックなんかじゃないよ」
「いえいえ、最初から最後までバランタイン17年のオン・ザ・ロックしか飲まないという方は胡寺さんしかいらっしゃらない。ストイックですよ」
「それをストイックっていうのかな。バカってことじゃないか」
大野は「いえいえ、ストイックとしか思えません」といって笑った。
「昔からバカだったんだよ。中学のときからサーフィンばかりやっていた。高校のときから付き合っていた、ほらさっき似てるっていっただろう、あんな感じの彼女にこう言われたんだ。大学4年で就職先を決めなきゃってときだった。会ってもサーフィンの話しかしない俺に『あなたなんか、一生サーフボードを抱いてればいいのよ。バカじゃない』って叱られたことがある」
「やはり。胡寺さんは、なるほど。サーファーってストイックですよね」
「あなたはサーフィンやったことがあるの」
「実はここ4、5年、はまっているんですよ。休みの日は必ず」
「あっ、そうなの。そうなんだ。はじめて知った」
「ええ、これまで、お客様に打ち明けたことはありません」
「俺もはじめて打ち明けた。それで、どうしてはまったの」
「うまく言えませんが、非日常だから、でしょうか」
まさに。大野は言い当てている。海の上に浮かんでいることだけでも非日常だ。さらには、一度波に乗ると、無音ともいえる非日常がある。音がないわけではない。波を切るシャーッといった感覚だけが身体に伝わってはくる。あとは何も聴こえない。
夕香はいつもクルマの中で待っていた。胡寺が海にいる間、いつもカーラジオをつけて、毛糸の帽子を編んでいたり、本を読んでいた。キルティングのボードケースは彼女の手製だった。
大学を卒業すると夕香はホテルに就職して、望んでいた企画広報の仕事で忙しくなった。胡寺はサーファー仲間の紹介で音響技術を専門にする制作会社にアルバイトで入り、訳のわからないうちにラジオの音楽番組の構成の仕事に首を突っ込むことになった。
社会人になって2年ほど立ち、お互いの仕事のペースがつかめると、結婚という二文字を気にするようになる。だが夕香の父親が大反対した。
フリーで収入がまったく安定しない、というか稼ぎが少なく将来の見通しもない胡寺に、どんな親であっても娘を渡したくなかっただろう。暇な時間も多く、相変わらず海を愛しつづけていたのも彼女の父にとっては不愉快だった。
夕香は家を出て、胡寺の狭いワンルームのアパートへ転がりこんできた。驚いている胡寺に向かって、「大きなスーツケースふたつで嫁入りよ」と言って啖呵を切り、ひとつを開けて取り出したのが1本のウイスキーボトルだった。
「なんかさ、お父さんに意地悪したかったんだけれど、慌てていたから大好きなウイスキーを失敬するくらしか思いつかなかった」
その夜、バランタイン17年で三三九度の契りを交わした。だがそれから三ヵ月ほどで夕香は入院してしまう。白血病だった。治療費など胡寺に支払えるはずもなく、彼女の父親にすがるしかない。惨めだった。
闘病生活での彼女の支えは、胡寺が台本を書くラジオ番組だった。彼女のベッドの脇で練った番組が流れるのを唯一の楽しみにしていた。
「俺は、バカだから。カッコウ悪いから。ただ書きつづけ、ただバラン17年を飲みつづける。ひとつのことしかできないんだ」
胡寺がそう言うと、大野が真剣な眼差しで返してきた。
「ただ、そうなんでしょうか。胡寺さんのお仕事やお酒の飲まれ方を、ただ、とは、わたしは思っていません」
苦笑いで応えるしかなかった。東京ミッドタウンから眺める景色はまだ淡い輝きを残していた。
今日も長い一日だった。
バランタイン17年を口にする。甘美さの中に、温もりを感じる。
(第16回「長い一日」了)







*この物語は、実在するホテル、ホテルバーおよびバーテンダー以外の登場人物はすべて架空であり、フィクションです。
登場人物
胡寺(脚本家)
 協力 ザ・リッツ・カールトン東京
協力 ザ・リッツ・カールトン東京