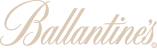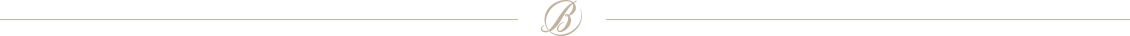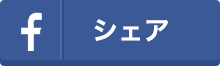「スコットランドでは雨に降られた日もあったでしょう」
バーテンダーの小嶋に、わたしはこう問いかけた。彼はこの2月に1週間ほど休暇を取り、スコットランドを旅してきている。
「降られました。あちらでは一日のうちに晴れのち曇り、一時雨という空模様が当たり前ですから」
「ほう、そうなんですか。ところでスコットランドの雨の色は何色でした」
「それがなんと、ウイスキー色。そのグラスの中と同じ金色というか、そう、ゴールデンブラウンに輝いているんです」
真顔で言う小嶋の目を覗き込むようにして見つめ返すと、彼はすぐに「ごめんなさい」と謝った。
今日も小嶋との他愛もない会話でウイスキーを飲む。自分の店が定休日の水曜、特別な予定がない限り午後の2時間をBar Capriで寛ぐ。小嶋とは10歳ほど歳が離れてはいるがウマが合い、爽やかな好青年に成長した弟と接しているような気がする。
「でも榊原さん、どうして雨の色なんか気になさるんですか」
「娘に今朝、雨の色は何色なの、って聞かれて困っちゃいました」
「大変だ。なんて説明すればいいのでしょうね」
幼稚園の年長になった娘は小学3年生の兄からも、母親からも納得のいく回答が得られなかったらしい。
「それで、なんて答えられたのですか」
小嶋は興味津々の様子だ。
「そのときの自分のこころ、気持ちの色だって。だからすべての人の気持ちに染まるように透明なのだ、と言っておきました」
「素敵な答えですね。榊原さん、詩人ですよ。それ、戴きです。とはいえ、お嬢ちゃん、理解してくださいましたか」
「今夜は家族で焼き肉屋さんで夕飯を食べる予定なので、娘は、じゃあ今日の雨は焼き肉色だ、ってはしゃいでいました」
「カワイイ。なんだか、こちらの気持ちまで明るくなります」
親の言うことは素直に聞けないが、親戚のおじさんの話には耳を傾ける。そんな時間が20数年前の午後1時過ぎにあった。
伯父は自分の娘の結婚披露宴を前にして、わたしをバーに誘った。花嫁の父はいたたまれないのだろうと察しながら、こんな昼間からバーが開いていることへの驚きと好奇心に胸が高鳴る。
スコッチウイスキーをオーダーした伯父は、「学生なんぞに飲ませるべき酒ではないが、今日はゆるす」と言った。酒への関心はわたしにはなく、バックバーを彩る絵画に圧倒され、見入ってしまう。パリ画壇の具象画の巨匠ポール・アイズピリが描いたカプリ島をテーマにした7連作油彩であることは後で知った。
なんて素敵なバーだろう。居酒屋しか知らなかったので、いきなり未知の世界へワープしたような錯覚に陥った。
「6月の花嫁かなんか知らないが、梅雨入り前だというのに、しとしと降ってきちまったじゃないか。だから5月に挙げろって俺は言ったんだ」
やはり花嫁の父の悲哀を聞かされるのだ、と覚悟したところへ、次に伯父が発した言葉の矛先はわたしだった。
「聞いたよ。店を継ぎたいんだって。立派だが、大学を中退するっていうのはようわからん。いま3年生か。六法全書は眠たいんだろう」
その頃、父と大喧嘩をしていた。少しは名の知られた三代つづく蕎麦屋で、わたしが大学を中退して四代目を継ぎたいと申し出ると、父は湯呑みを叩き割るほどに怒りまくった。わたしだけでなく、妹も弟も継がなくていい。廃業しても構わない。店にしがみつくな。それが父の言い分だった。
奇妙な家系で、二代目も三代目も先代に反対されながら店を継ぎ、子供には違う世界で生きることを望んだ。二代目の祖父はジャズドラマーからの転身、三代目の父は建築家を志しながら大学を中退した。
わたしはというと伯父が見抜いた通りだった。六法全書を開くと、司法試験を受けて弁護士を目指す自分の姿が消え去り、睡魔が襲う。抗おうとすると店に立つ父親の姿が浮かび、それがやがて自分の姿に変身する。六法全書はあるべき自然な姿を教えてくれていた。
「おまえの両親から説得を頼まれていた。正直に言うと、おまえの好きなようにしていいと思うが、とにかく大学だけは卒業しろ。そんでどっかに就職しちまえ。それでも店を継ぎたいと言いつづければ、親は折れる」
結局、筋書き通りになったのだが、そのとき伯父が面白いことを言った。
「おい、今日の雨、おまえにとっては何色だ」
わたしが「雨は水滴、透明だよ」と返すと、「ちっ、法科の学生はセンシティブじゃないな。雨にはこころの色が映るんだ」と言ってこうつづけた。
「今日は花嫁の父には涙雨で、俺のこころはブルーだと思っているのだろうが、大間違い。薔薇色よ。娘が早く出て行ってくれて嬉しい。祝いの薔薇色の雨だ」
「じゃあ、雨の色はいつも違うんですか」
「そうさ。仕事が充実しているときは金色だ。ただし、金色に輝く雨を見ることができるのは、天職を授かったものだけだ」
子供だましのような屁理屈を聞かされて嫌になりかけたとき、背後のテーブル席からブルースの歌声が小さく聴こえてきた。黒人の4人の男たちだった。軽く数フレーズをコーラスで口ずさむと楽し気に笑い合い、再び静寂が訪れた。
「アメリカの有名なジャズメンだ。ドラマーだった爺さんに可愛がられているおまえなら、知っているだろう」
わたしは頷きながら、胸が震えるほどの感動を覚えていた。背筋から脳天まで痺れが走っている。ここは日本じゃない。
「彼らにも金色の雨が降る。しかしあいつら、上等なスコッチを飲んでいるな」
そう言って伯父はウイスキーを飲み干し、「説得は失敗。これから披露宴で花嫁の父を感動的に演じなければならん」と腰を上げた。わたしには彼らの飲んでいたスコッチのボトルが目に焼き付いた。
小嶋が二杯目のバランタイン17年をグラスに注いだ。
「ありがとう。ところで差し支えなければ、君がホテルニューオータニに就職した理由を教えてくれませんか」
「世界の名酒が扱えるのはもちろん、世界的に著名なお客様がご宿泊され、バーで寛がれる。バーテンダーにとってはとても魅力的ですよ」
大学時代に街場のバーでアルバイトをはじめ、卒業してもバーテンダーをつづけた。その後しばらく海外を旅してまわり、帰国後にホテルニューオータニに入社したことをはじめて知った。
「天職ですね。だから小嶋さんには金色の雨といった表現ができるのかもしれません」
「おっしゃっている意味がよくわかりませんが、勘弁してください。天職に就いていらっしゃるのは榊原さんです。わたしは榊原さんのような謙虚な職人の方を尊敬しています」
小嶋が真剣に言う。
照れ臭くなってしまったわたしは、Bar Capriに憧れ、17年もののスコッチに憧れた理由を話せなくなった。
それにまだ40代。尊敬される職人にはほど遠い。ようやく父のこころ、伯父が伝えたかったことが理解できるようになってきた。生半可な気持ちで跡は継げない。ひとつの道を歩み、極めようとしながら店を守りつづける厳しさが、歳を重ねるほどに身に沁みる。
ウイスキーを口に含むと、あのときのブルースが耳の奥によみがえった。
帰り道、雨は何色だろうか。
(第3回「金色の雨」了)








*この物語は、実在するホテル、ホテルバーおよびバーテンダー以外の登場人物はすべて架空であり、フィクションです。
登場人物
榊原(蕎麦店四代目)
 協力 ホテルニューオータニ
協力 ホテルニューオータニ