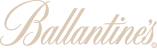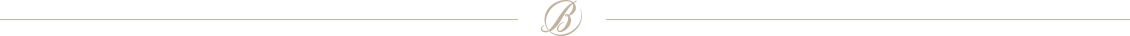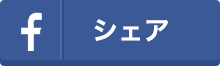ようやく、ひと心地ついた。いつものつまみとウイスキーが旅の疲れを癒す。
「いいねぇ、江戸の味は。日本橋の佃煮は日本一おいしい。ウイスキーと合う。やっぱ日本がいい」
はしたない、と思いつつも舌鼓を打ちながらしみじみ言うと、バーテンダーの植薗が苦笑した。
「なによ、何がおかしいの」
「おやじくさいなぁ、里美さん。レディなんですから。まだ他にお客さまがいらっしゃらないからよろしいんですけれど」
「憎まれ口を叩くアラフォーの女を、レディとして扱ってくれてありがとう」
「うちの女性のお客様は皆さん素敵なレディです」
いつもの飄々とした植薗の受け答えに、地元に帰ってきた実感が深まる。
「いいじゃないの。成田からまっしぐらにここへ来たのよ」
「営業開始とともにご入店いただき、ありがとうございます。ただ、イギリス帰りですぐにロイヤルスコッツという名のバーを目指し、そこでスコッチを飲みながら日本がいいっておっしゃる方も珍しい」
「それもそうね。でも、悪いのはこのホテルの立地とバーよ。東京シティエアターミナルに隣接しているのがいけないし、日本橋老舗おつまみセットなんて佃煮のメニューがあるのもいけない」
「いけない、ですか」
「まあ、いいじゃん、細かいことは。成田に着いた途端に頭に浮かんだのが、佃煮で一杯だったんだから」
植薗はまた苦笑しながら「それは居酒屋でしょう」と言って間を置き、「大丈夫ですか。まっすぐ家に帰らなくて」とつづけた。
自宅は人形町だ。水天宮前にあるこのロイヤルパークホテルからは歩いて10分もかからない。バー好きの両親と月に二、三度はロイヤルスコッツを訪れている。地下鉄の駅とも連結しているから便利で、会社帰りに立ち寄り、ひとりウイスキーを飲むこともある。
「父と母が来たのね」
「ええ。つい3日前、お見えになりました」
他人に話すことではない、と思うのだが、仕方がない。生まれも育ちも下町の父母は、英国の格調高い社交クラブのような内装を施したホテルバーでさえ近所のお仲間さんで、バーテンダーになんでも気軽に喋ってしまう。
婚活もせず、自宅と会社の往復を繰り返している。化粧品会社で輸入化粧品部門に長く在籍し、一応は香水の広報PR担当のエキスパートらしいのだが、浮いた話のひとつもない。そんなひとり娘に対して、両親はこれまで何も言わなかった。ところが父が定年退職後しばらくして時間を持て余すようになってから、何気なくプレッシャーをかけてくるようになる。
先月、両親がついに見合いの話を切り出した。相手の写真さえ見ようとしない娘に両親は苛立った。しつこさに嫌気がさし、「もうわかった。家を出てひとり暮らしをする。放っといて」と言うと、話が余計にこじれた。
上司から有給休暇を取ってくれと泣きつかれていたし、忙しさも一段落した時だったから、逃げ出すようにオリンピック開催前のロンドンに旅立った。
「里美さん、ほんとうは、まっすぐ家に帰りたくないんでしょう」
植薗が痛いところを突いてくる。
「うん。佃煮とウイスキーで、現実逃避。駄目かな」
「いいんじゃないですか。案外、帰り道にいいことがあったりして」
「ある訳ないじゃん。相手がわたしだからって、またいい加減な対応をして」
「でも、今夜は七夕。何かが、起こるかもしれません。キャリーバッグをガラガラ引きながら歩いていたら転んでしまう。助け起こしてくれたのが、なんと凄いイケメン。そこから恋がはじまる」
「話がチープ。それよりさ、もうすぐ5時半。お寿司屋さんが開くでしょう。いつもの握りのセット、オーダーしてちょうだい。お腹が減っちゃった」
苦笑しながら「かしこまりました」と植薗は対応した。
あさり、たらこ、かつお。それぞれの佃煮をひと口食べる度にウイスキーを啜る。すると穏やかな心持ちになってきた。親の言うことも聞いてみようか。相手に会うだけ会えば、親の気持ちも安らぐかもしれない。
箱入り娘として育てられた訳でもなく、仕事で何かを達成しようというほどの高い意識もなく、毎日を過ごしていたらここまできてしまった。
単純にひとりがいいのだ。イギリスの女流作家ヴァージニア・ウルフの『私ひとりの部屋』だっただろうか。精神の独立のためには自分だけの空間と収入が不可欠だ、と書いてあったような。自立しよう、なんていう芯の強さは持ち合わせていないけど、わたしひとりの部屋があれば、それでいい。わたしのこころの部屋にはいつも章ちゃんがいる。
彼は天体研究の権威で、世界中の天文学の研究所に招聘されつづけている。去年まではNASAにいて、いまは南米だ。2、3年に一度くらいしか会えないけれど、インターネットがあるから助かっている。
両親は娘が隣の家の子を慕いつづけているとは思いもよらないだろう。7歳年上の章ちゃんに、わたしはよちよち歩きの頃からおにいちゃん、おにいちゃんとつきまとっていたのに、気づきもしない。
章ちゃんは子供の頃から空が好きで、果てしない宇宙について考えてばかりいた。雨の日は空から落ちてくる滴を数えでもするかのような気難しい顔をし、晴れの日は南半球じゃ太陽は北に上がるとでも言いたそうに、こそばゆいような顔をしていた。でも、わたしの前ではいつも明るく優しかった。
家では章ちゃんのことを天体望遠鏡と呼んでいる。高校に入学した頃の章ちゃんを父が、「秀才が空ばっか見ているから、あんなにひょろい男になっちまったんだ。ほら、誰が使うのかわからんが、よく学校の理科の実験室に置いてある、細長い天体望遠鏡みたいだろ」と評してからだ。
天体望遠鏡が古くなって、どこかの研究所に収まるしかなくなったとき、わたしが面倒をみるって約束してある。でもまだまだ働き盛り。あと20年くらいは落ち着かないか。
「おかわりをつくりましょう。初恋の人を慕いつづけるレディのために、七夕の夜空に薫る一杯を」
植薗が急に真剣な表情で言った。
「なに。それ、どういうこと」
「香水の仕事をしているのなら、素敵な香りのウイスキーを飲みなさいって、大好きな方から言われたんでしょう」
「いつ。いつ、わたし、そんな話をした」
「3、4年前の土曜日です。ひとりで、ちょっといい酔い心地でいらっしゃいました。会社の後輩の結婚式があって、その2次会帰りとかで。そのとき里美さん、ずっと慕っている人がいるって。たしか天体望遠鏡とか。もう、覚えていらっしゃらないですよね」
「まじで。あちぃ、大失敗してたんだ」
火の粉が飛び散るほどに顔が熱くなった。
「そこが酒好きの、可愛いところです。気にしないでください」
植薗は飄々とそう言うと、優しくしなやかな手つきでバランタイン17年をグラスに注いだ。甘く華やかな香りが浮遊しはじめた。
「ありがとう」
感謝の気持ちを告げると、植薗は穏やかに微笑んで「お寿司、もうすぐご用意できま す」と言った。
(第4回「七夕に薫る」了)








*この物語は、実在するホテル、ホテルバーおよびバーテンダー以外の登場人物はすべて架空であり、フィクションです。
登場人物
里美(化粧品会社勤務)
 協力 株式会社ロイヤルパークホテル
協力 株式会社ロイヤルパークホテル