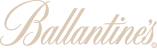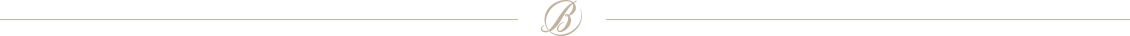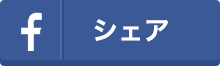いつもの癖で、マーブルのカウンターを見つめる。濃紺地に刷毛で払ったような白い奔放な模様を幾夜も眺めているが、飽くことがない。その上ではしなやかなステアから紅いカクテルがつくられている。
カクテルグラスに紅が注がれ、ピンに刺したマラスキーノチェリーが沈められると、一輪の薔薇が咲いたような気がした。
「スコッチ・マンハッタンです。どうぞ」
バーテンダーの北原が微笑みながら言った。「ありがとう」と緒方は答え、ひと口啜る。
シルキーな舌触り。ふくよかなブレンデッドウイスキーにスイートベルモットの甘さがほどよく溶け込んでいる。
「緒方さん、何かいいことでもありましたか」
北原が快活に声をかけてきた。
「はて、いいのか、どうか」
「でも、悪いことではない。そうでしょう」
「なんで、ぼくの気持ち、わかるん」
「わかりますよ。このカクテルを飲まれるときは、気持ちを穏やかにされたいときか、何か特別なことがあった日です。今夜の表情には、チョイワル建築家のダンディズムの相がありますね」
「チョイワルって、なんやねん。きみ、いつから占い師になったん。それにしても、バーテンダーはすべてお見通しなんやね」
ザ・リッツ・カールトン大阪のザ・バーに寛ぎを求めるようになってちょうど7年になる。はじめてカウンター席に着いたのは、マンハッタンに暮らす典子との10年にもおよぶ別居生活に終止符を打ち、ニューヨークから帰国してまもなくの8月の終わりだった。
遠過ぎる距離と長い空白の時間。40を過ぎた男と、40前の女が、このまま夫婦でありつづける必然性はなかったのだが、離婚とともに緒方のこころの壷はひび割れていく。自分の愚かさ、稚拙さを実感する日々がつづく。
すべてに気力が失せて、マンハッタンで滞在したホテル、ザ・リッツ・カールトン ニューヨーク セントラルパークでの典子との時間をなぞるかのようにザ・バーへと足を運びはじめる。
入り口の扉はセントラルパーク・サウスにあるホテルと同じで自動ドアではなく、ベルボーイが出迎えて開けてくれる。エントランスはもとより、内装は一貫して18世紀英国のジョージアンスタイルを模してあり、小ぢんまりとしていて瀟洒でエレガントだ。セントラルパークと変わらぬ古典の趣、そしてスタッフのホスピタリティがあった。
何よりも北原がつくるロブ・ロイとも呼ばれるスコッチ・マンハッタンが気に入った。
ザ・バーで過ごす時間だけはこころの壷が潤うのだった。
セントラルパークのリッツ・カールトンには2週間滞在した。ブロードウエイで舞台美術の仕事をしている典子は忙しく、緒方はひとり、ホテルのバーで時間をつぶすことが多かった。彼女が時間の取れた夜は、カウンターで長時間語り合った。
妻が渡米したのは、夫への愛が失せた訳ではない。夫が仕事にしか興味がないのならば、自分も好きな道を極める決断をする。しかし夫は、妻が学生のように数年留学する程度に甘く考えていた。夫には独善的な自信だけがあった。妻は夫をライバルに選んだのだが、夫はそれに気づくことはなかった。
バーで語り合うほどに典子の人間性が高まっていることを実感する。そしていざ離婚となると、緒方はそれまでと同様、典子の醸し出す明晰さを潜めたおっとりとした魅力、長い空白の寂寞感を一瞬にして忘れさせてしまう愛くるしさへの未練を断ち切れなくなる。
ただ今回だけは彼女の気持ちを長年察することができなかった鈍感さや傲慢さを恥じる自分がいて、こころの壷に苦い澱みが生じていた。
バランタイン17年のオン・ザ・ロックを好む緒方に、ある夜、バーテンダーが「たまには気分転換をされてみたらいかがでしょう。柔らかい味わいですよ」と気遣い、スコッチ・マンハッタンをつくってくれた。そのときも緒方はひとりだったのだが、よほど冴えない顔をしていたのだろう。
すすめられたバランタイン17年ベースのスコッチ・マンハッタンはこころの襞に染みて、苦い澱みを洗い流してくれた。自分自身が変わらなければならない。一度、ゼロにリセットするのだ。そう決心がついた。
最後の夜は朝まで一緒に過ごした。日が昇りはじめたばかりの時刻、典子の感嘆の声で目覚めた。
窓際に立った典子は振り返ると「ごめんね。起こしちゃった。セントラルパークがあまりにも奇麗だから」と言った。純白のバスローブから伸びた彼女の肢体が朝の光を浴びて眩しかった。
ベッドから身体を起こし、窓辺へと歩み寄って目を見張る。セントラルパークに朝霧が白く立ちこめていた。
深夜、摩天楼のオアシスを濡らしたまま眠りこけてしまった雨露が、日の出の光に目覚めさせられる様子に地球上のあらゆる生命体の息吹のようなものを感じた。あまりにも神秘的で、静かで美しく優しいエネルギーに満ちていた。
朝焼けの紅い光がオレンジ色に明るくなっていく間に霧は白からピンク色に染まりながら薄らぎ、次第に消えて行く。その時の流れの中で木々に茂った夏の緑がくっきりと姿を現す。
「どんな舞台芸術も、こんなふうには創りあげられない。自然って凄い。お日さんのチカラって強いんだな」
典子は起き抜けのかすれた声で穏やかに言うと、手をつないできた。
「きみは仕事のことしか頭にないんやね」
「それは、あなたでしょう。わたしには、まだ達成感がないの。でもいつか、こうして霧が晴れていくようにこころが満たされる時がきたなら、何が待っているのかしら。何が姿を見せるんだろう」
ふたりは手をつないだまま押し黙り、セントラルパークを見つめつづけた。やがて典子は朝食も摂らずにブロードウエイの仕事場へ直行した。
「9月がまた来るね。今年も曳くんやろ」
緒方は北原から聞く、だんじり祭りの話が好きだ。
「もちろんです。岸和田に暮らす男がだんじりを曳かんことには、ね」
「ひとつ聞きたいんやけど、だんじりが終わったあと、なんていうか、祭りのあとの切ないような、抜け殻みたいな気持ちにならへんの」
「そんな気持ちもなくはないんですが、わたしの場合は不思議ですね。なんやら脱皮したような、生まれ変わったような、また来年のだんじりまで、俺、仕事頑張るわ、といった新鮮な気持ちのほうが強いんです。真っ白な感覚です」
北原はプライベートの話になると素の顔を見せてくれる。
「9月に、ゼロになる、か」
緒方はそう呟いて、ようやく生まれ変われそうな自分を笑った。
「オン・ザ・ロックの前に、こちらをどうぞ。バランタイン・ミストです」
「これ、ぼくのためにつくってくれていたの。そうなん」
北原が笑顔で頷く。クラッシュドアイスがぎっしりと詰まったグラスの中はゴールデンブラウンに染まっていた。氷の粒の上に乗ったオレンジピールの鮮やかさに新たな息吹を感じた。
「涼しげで、ええなぁ」
「いつものバランタイン17年のロックとはまたひと味ちがいます。生まれ変わった気分になります」
グラスの表面を覆うミストが、緒方に7年前のセントラルパークの朝をよみがえらせた。
9月、典子が帰国する。太一という名の6歳になる男の子が一緒だ。
(第5回「八月のミスト」了)









*この物語は、実在するホテル、ホテルバーおよびバーテンダー以外の登場人物はすべて架空であり、フィクションです。
登場人物
緒方(建築家)
 協力 ザ・リッツ・カールトン大阪
協力 ザ・リッツ・カールトン大阪