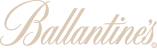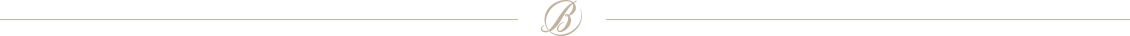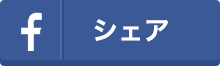習いはじめた茶道の帰り、大阪新阪急ホテルの間近でタクシーを降りて、梅田の地下街からバー リードに向かった。
午前に自宅を出て乗った阪急電車内でも、横断歩道で信号待ちをしていても声をかけられた。いつもの通り、「きれいやね」「素敵やわ」の声の主は年配のオバチャンたちだが、悪い気はしなかったし、男性からの視線も感じていた。ところが、さらに今日は「女優さんですか」と声をかけられ、さすがに照れくささを通り越し、自分が目立ちたがり屋のようで逃げ出したい気分に陥る。だからホテルの1階ロビーに足を踏み入れるのは気が引けた。
着物の色調のせいだとは思う。紫苑(しおん)色の単衣の小紋に、帯は萩と桔梗をあしらった白地の名古屋。帯締めは琥珀色。これまではやや渋めの装いが多かったのだが、柔らかくて爽やかな印象の今日のコーディネートは9月初旬のいましかないのだ。
新聞社を辞め、週3日花屋でバイトをしながら、取材で知り合った茶の湯の大先生のところに週2日通っているのだが、和装で出かけると必ず声をかけられる。「イケてる女になりなさい」が口癖の大先生は品格と芯のある何事にも筋の通った老女で、すでに引退してお弟子さんは取っていないのにもかかわらず、特別に着物の着付けや料理までをも徹底的に教え込んでくれる。紫苑色の単衣も大先生の見立てだ。
着物だとよく声をかけられ、恥ずかしい、と大先生に言うと、「イケてる女に成長している証拠。毅然としていなさい」と笑われる。
ウイスキーのハイボールで喉を潤し、退職後半年ものご無沙汰を謝りながらのそんな近況報告を、バーテンダーの寺澤愛里は喜んで聞いてくれている。
「自意識過剰かしら」
「そんなことありません。わたしも、どこかのセレブかと思い、胸が高鳴りました。なんで女性のお客様に、こんなにドキドキしなくてはいけないのかしら。結衣さん、素敵過ぎるわ」
「ほんとう。嘘やない」
「スタイルがよくて、ビジネススーツ姿がとてもお似合いでしたから着物姿も映えますね。それに、営業開始の4時過ぎの登場ははじめてでしょう。これまでは早くて10時過ぎで、いつも疲れた様子でしたのに今日は別人のよう」
「あら、いやだ。疲れていたかしら。でも、たしかに和装は人の印象を変える。とはいえ随分と無理をしているの。これまでの貯金とわずかな退職金をほとんど着物に投資しているんだから」
久しぶりの寺澤とのガールズ・トークに気持ちが和んだ。
「淡い紫色、とっても素敵。まさに、はんなり。品があって、それでいて暑さの残るいまの季節に涼風を運んでくるような。バーに可憐な花が咲いたみたい。赤いこのカウンターとも合っている。これからも和装でちょくちょく顔をみせてください」
「わかったわ。それよりも、久しぶりにロックで飲ませてください」
10年あまり勤めた新聞社で長く文化欄担当の記者をしていた。バー リードには仕事関係者と訪れ、好きになったシングルモルトウイスキーをいろいろ飲み比べては遅くなり、よく阪急電車の最終で帰った。寺澤とは顔馴染みだったが、とくに親しくなったのは3年ほど前。学生時代から付き合っていた恋人と別れてすぐの頃だった。
海外赴任が決まりそうになった商社マンの彼氏からプロポーズされたのに、すぐに「はい」と返事ができなかった。この日のために、結婚するために、いままで仕事をしてきたような気がして、何故だか素直になれない。待っていたはずなのに、待っていなかったのだ。ならば、仕事を選ぶのか、と問われると首を振るしかない。自分でもよくわからない。釈然としない。
なかなか返事をもらえない彼は苛立って「ぼくなんかおらへんでも生きていけるんやろ」と言った。生きるとかなんとかじゃなくて、と応えようとしたのだが、その後につづく言葉が見つからなかった。
彼と別れてすぐにバー リードのカウンター席にひとりで座った。シングルモルトを2杯ほど飲んで、次の一杯を思案していたら寺澤が声をかけてきた。
「今夜はピッチが早いですよ。タフなお酒をそんなに急いで飲んでは。上質なブレンデッドをゆったりと味わってみてはいかがでしょう」
すすめられてプレミアム・ブレンデッドを飲んだ。しなやかで懐が深い感覚に包まれると、こころの岸辺が熱くなり、何かがあふれ出した。いったい自分は何をしたいのだろう。このまま年齢を重ねていくのが急に怖くなった。気がつくとロックグラスに涙がぽたぽたと落ちていた。
寺澤は戸惑いながらも、グラスの脇にさり気なくおしぼりを置いてくれた。バーテンダーの優しさに、また涙があふれた。
それからは気をゆるし、何でも話せるようになる。いくつか年下の寺澤の立ち姿に自分よりも大人を感じることもあり、学ぶことも多い。
「あれ、愛里さん、いつものロックと違う」
そう問いかけると、「結衣さんがお見えになるのをお待ちしていました。どうしても試していただきたいカクテルです」と言って、ビターズ・ボトルに入った琥珀色の液体をバランタイン17年のオン・ザ・ロックに5回ほど振りかけた。液体はバランタイン17年にオレンジ・ピールを1日ほど漬け込んだものらしい。
「名付けて、レディ・バランタイン。折れそうで折れない、細い青竹のようにしなやかで芯のある、素敵な女性をイメージしてつくってみました。もちろん結衣さんがモデルです」
「ええっ、嘘でしょう。記者時代なら、恥じらいながらも元気づけられたでしょうけど」
「そんなことありません。だって仕事を辞めても、茶道を学ぼうという気概がある人なんですもの。きっとまた、新しい何かを自分の中に見いだされるような気がします」
「愛里さん、買いかぶりやわ」
「お話はしばらく置いといて、とにかく、試していただけますか」
香りを嗅ぎ、ゆっくりと口に含む。甘美さの中にフルーティーさもあるバランタインにオレンジの感覚が加味され、華やぎがありながら思いのほか引き締まった味わいだった。
「おいしい、とっても。ありがとう。これからも用意しておいてくださる」
「もちろん。いつお見えになってもいいようにしておきます」
「うん、お願い。それはそうと、茶道をはじめたのは愛里さんの影響よ。あなたがやっていたから、わたしも体験してみようと。紫苑の花言葉はね、君を忘れず、なんやて。わたしは、君の茶道を忘れず、だったの」
「だったの、って、いややわ。高校時代、頼まれて茶道部に名前を貸しただけ。ほんのちょっとかじっただけやのに。以前、そう話したはずです。結衣さんの場合は忘れずじゃなくて、忘れるでしょう」
笑い合いながら、このコーディネートで、やはりよかったと思った。中秋の頃に咲く紫苑には十五夜草、思い草といった別名がある、と教えてくれた大先生に感謝した。
こうして気遣ってくれて、カクテルまで考えてくれるバーテンダーがいる。バーを愛する男の人たちの気持ちがわかるような気がした。イケてる女もいいけれど、男になって存分にウイスキーを飲んでみたい、とも思う。
(第6回「紫苑咲くグラス」了)








*この物語は、実在するホテル、ホテルバーおよびバーテンダー以外の登場人物はすべて架空であり、フィクションです。
登場人物
結衣(家事手伝い)
 協力 大阪新阪急ホテル
協力 大阪新阪急ホテル